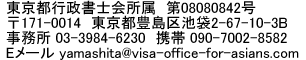早稲田大学大学院日本語教育研究科の修士課程(修士論文の題目:刑事施設における日本語教育は誰のためのものなのか―外国人受刑者に対する日本語教育の現状と課題―)を修了致しました。今後は、行政書士として活動していくことに加え、中長期間在留する外国人の方々のために、日本語教師としても活動していきます。具体的には、留学生のための日本語教育を中心に、生活者やビジネスマンのための日本語教育、外国人児童のための教科学習支援等、日本語教育の領域においても、外国人の方々のお役に立つことができればと考えています。
2015年08月31日(月)から09月11日(金)までの2週間、早稲田大学のSENDプログラムを通じ、タイ王国東北部にあるコーンケン(Khon Kaen)大学の人文社会学部日本語学科にて、日本語教育の実習を行ってきました。現地では、直接法(日本語)での指導だけでなく、タイ語での指導も行ってきました。この実習で得た経験や知見を、日本に在留する非漢字文化圏日本語学習者の指導にも活かしていきます。
2015年5月29日(金)、言語文化教育研究学会の第32回月例会(場所:早稲田大学早稲田キャンパス22号館601教室)において口頭発表を行いました。題目は、「外国人犯罪者を生み出さないために日本語教育ができることは何か」でした。これに出席した会員の方々から様々なご意見を頂きました。ありがとうございました。
2015年3月14日には、移民政策学会の2014年度春季大会(会場:早稲田大学早稲田キャンパス15号館04教室)において、また、同月28日には、早稲田大学日本語教育学会の2015年春季大会(会場:早稲田大学早稲田キャンパス22号館201教室)において、口頭発表を行いました。前者における発表の題目は、「外国人受刑者に対する日本語教育の現状と課題」、後者における発表の題目は、「刑事施設における日本語教育は誰のためのものなのか―府中刑務所と栃木刑務所の事例から―」でした。
①「移民の若者の社会的排除―日系ブラジル人の場合」能勢桂介先生(立命館大学)、②「企業の積極的海外展開に向けた雇用戦略~外国人雇用と日本人雇用は補完的になり得るか~」長谷川理映先生(関西学院大学大学院)、③「滞在資格付与の正統性と政治的権利―非正規滞在者の法的地位についての政治哲学的考察―」岸見太一先生(早稲田大学大学院・日本学術振興会特別研究員)、④「イギリス入管収容施設における被収容者処遇の実態(日本の状況と比較して)」駒井知会先生(弁護士)・児玉晃一先生(弁護士)、⑤「国境管理政策と越境の持つ社会経済的意味―シンガポール・マレーシア陸路国境の事例―」石井由香先生(立命館アジア太平洋大学)。
会場には私の報告にも関心を持って下さる方々がおり、今後業務を遂行していく上で大きな励みとなりました。